監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
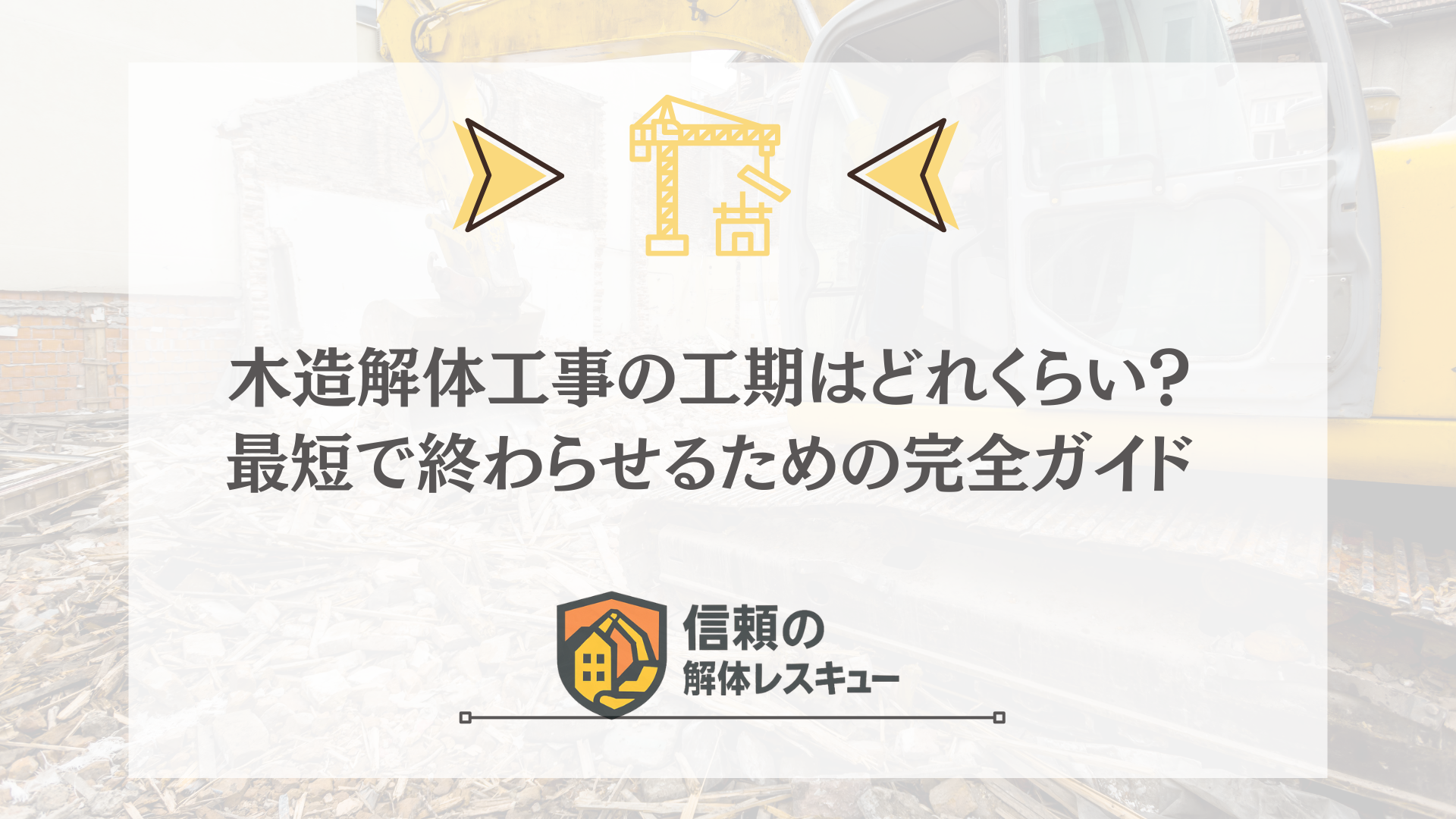
監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
木造住宅の解体は「約1〜2週間」が目安といわれますが、実際の工期は建物の構造・敷地条件・業者の段取りによって大きく変わります。この記事では、木造解体の標準的な期間から、工期が長引く原因、短縮のコツまでを、1000件以上の実績を持つ専門業者の視点でわかりやすく解説します。
木造解体の「作業期間」は、一般的な30坪程度の住宅で7〜10日が目安です。ただし、これはあくまで重機が現場に入ってから更地にするまでの日数です。平屋か二階建てか、敷地が広いか広いかといった条件で工期は変動します。大切なのは、この作業期間の前に「準備期間」が別途必要になることです。
標準的な30坪・二階建ての木造住宅の場合、解体作業は7〜10日程度で完了します。この工期には、以下の作業がすべて含まれます。
ただし、これはあくまで作業がスムーズに進んだ場合の目安です。
工期は、延床面積が同じでも平屋より二階建ての方が長くなる傾向があります。理由は、高さがある分離れた場所への配慮が必要となり、養生足場が大掛かりになるためです。また、解体作業も屋根から順に一層ずつ慎重に進める必要があり、高所作業が伴うため安全確保により時間を使います。例えば、同じ30坪でも平屋なら5〜7日、二階建てなら7〜10日と、数日の差が出ることが一般的です。工期は床面積だけでなく「高さ」にも影響されるのです。
工期を大きく左右するのが、周囲の建物との距離や敷地の立地条件です。例えば、住宅密集地で隣家との隙間がほとんどない現場では、重機が使えず「手壊し」作業の割合が増えるため、工期は大幅に延びます。また、現場までの道が狭く(狭隘道路)、大型の重機やダンプが進入できない場合、小型の重機やトラックで何度も往復して作業する必要があり、搬出作業だけで標準の1.5倍以上の時間がかかることも珍しくありません。
解体工事の「工期」を考える際、多くの方が作業期間だけを見がちです。しかし、実際には「業者への依頼」から「事前準備」「解体作業」「完了手続き」まで、すべてを含めたスケジュールが重要です。特に準備段階を怠ると、作業そのものが開始できないため、全体の流れを把握しておきましょう。
Step 1. 業者選定・見積もり期間(約2〜3週間)
解体を決意してから、実際に工事を依頼する業者を決めるまでが最初のステップです。この期間は焦らず、最低2〜3週間は確保してください。なぜなら、適正価格と信頼できる業者を見極めるために、3社以上の業者に「現地調査」を依頼し「相見積もり」を取る必要があるからです。現地調査の立ち会い、見積もり内容の精査、業者の対応比較など、納得して契約するために非常に重要な期間となります。
Step 2. ライフライン停止・事前申請(約1週間)
契約後、すぐに着工できるわけではありません。着工前に必須の手続きが多数あります。
特に「建設リサイクル法」の届出は、法律で着工の7日前までに義務付けられており、これが遅れれば工期も後ろ倒しになります。
Step 3. 不用品の整理・搬出(約1〜2週間)
工期に影響を与える要因として、施主様ご自身でコントロールできる最大のポイントが「不用品(残置物)」の整理です。建物内に残された家具、家電、衣類などは、原則として施主様の責任で事前に処分する必要があります。もし業者に処分を依頼すると、それらは「一般廃棄物」扱いとなり、高額な処分費がかかるだけでなく、その分別・搬出作業のために数日〜1週間程度、解体本体の工期が余計にかかってしまいます。
Step 4. 解体作業(約7〜10日間)
事前準備がすべて完了し、いよいよ着工です。これが一般的に「工期」と呼ばれる期間です。前述の通り、標準的な30坪の木造家屋であれば7〜10日程度です。工程は、まず養生足場を設置し、次に内装材を手作業で分別撤去します。その後、重機で建物本体を解体し、最後に地中の基礎コンクリートを掘り起こします。ただし、この作業日数は天候に大きく左右され、雨や強風が続けばその分、日数は延長されます。
Step 5. 整地・産廃処理・完了報告(約3日間)
建物と基礎がすべて無くなっても、まだ作業は終わりません。地面を平らにならす「整地」作業、敷地内に残った細かなガラ(破片)の清掃、そしてすべての廃棄物を処分場へ最終搬出する作業が残っています。これが完了して初めて、施主様による「完了確認(立ち会い)」となります。その後、業者から廃棄物処理の証明書(マニフェスト)や、法務局への滅失登記に必要な書類を受け取り、すべての工程が完了となります。
解体工事で最も重要なのは「事前準備」です。工期が遅れる原因の多くは、残置物の未処理や行政手続きの不備から生じます。私たちインシュアラは、お客様が行うべき準備も契約前に明確にご案内し、複雑な申請もワンストップで代行することで、スムーズな着工と最短工期を実現します。
解体工事の見積書には「工期〇日間」と書かれていますが、これはあくまで「予定」です。特に木造解体は、天候や現場の予期せぬ状況によって工期が長引くリスクが常につきまといます。
工期が長引く主な原因には、以下のようなものがあります。
あらかじめ、どのような場合に遅れが発生するのか、主な原因を把握しておくことが重要です。
工期が遅れる最も一般的な原因は「天候」です。特に雨や台風、強風の日は、作業を中断せざるを得ません。雨が降ると地盤が緩み、重機作業の危険性が増すほか、解体材が濡れて重くなり処分費用に影響することもあります。何より、強風時に作業を行うと、養生シートが煽られて足場が倒壊したり、埃やゴミが遠くまで飛散して近隣に多大なご迷惑をおかけしたりする危険があります。安全第一のため、悪天候時は作業を中止するのが鉄則です。
見積もり段階では予期できなかった「隠れたリスク」が、工期を大幅に遅らせる原因となります。その代表がアスベスト(石綿)です。事前調査で図面にないアスベストが発見された場合、法律に基づき、飛散防止のための厳重な隔離養生や専門的な除去作業が必要となり、工期は数日〜数週間単位で延長されます。また、基礎を撤去した際に、地中から昔の浄化槽やコンクリートガラなどの「地中埋設物」が出てきた場合も、その撤去・処分作業のために追加の工期が必要となります。
登記上は「木造」となっていても、過去の増改築によって一部が異なる構造になっているケースがあります。例えば、1階の車庫部分だけが鉄骨造(S造)になっていたり、地下室が鉄筋コンクリート造(RC造)になっていたりするパターンです。木造解体のつもりで重機や人員を手配しているため、頑丈な鉄骨やRC造を解体する機材や工法に対応できず、追加の手配で大幅なタイムロスと工期の延長が発生します。現地調査の精度が問われる部分です。
工期が遅れる原因は、現場や天候だけではありません。業者の「対応力不足」が原因となるケースも多いです。例えば、騒音や振動、埃に対する近隣挨拶や対策が不十分だったためにクレームが発生し、作業の一時中断を余儀なくされることがあります。また、建設リサイクル法の届出漏れや、前面道路の使用許可(道路使用許可)の申請不備など、業者が行うべき行政手続きの遅れによって、着工が遅れたり、工事中に指導が入って作業がストップしたりするケースもあります。
住宅密集地や昔からの市街地では、現場に面した道路(搬入経路)が非常に狭いことが工期に直結します。大型の重機や廃棄物を運ぶ10tダンプが進入できないため、小型の重機や2tトラックで作業せざるを得ません。小型重機は作業効率が低く、トラックは何度も往復して廃棄物を搬出する必要があるため、解体作業と搬出作業の両方で標準の1.5倍以上の工期がかかることもあります。この場合、公道に車両を停めるための「道路使用許可」の申請も必須です。
工期が長引く原因は多岐にわたりますが、それらのリスクを最小限に抑え、工期を短縮するために施主様ができる対策もあります。
工期短縮のポイントは以下の通りです。
天候のようにコントロールできないものもありますが、「業者選び」と「事前準備」を徹底することで、無駄な遅延を防ぎ、最短での解体完了を目指すことが可能です。
工期短縮の最大の鍵は、業者の「段取り力」と「リソース(資源)」です。木造解体の実績が豊富で、自社で重機やトラックを多数保有し、熟練の職人を十分に抱えている業者を選んでください。このような業者は、現場の状況判断が早く、段取りが非常にスムーズです。逆に、下請けに丸投げする業者や、重機をリースに頼っている業者は、急なトラブル対応が遅れたり、人員の手配がつかずに工期が延びたりしがちです。
もし解体のスケジュールに余裕があるならば、天候リスクが高い時期を避けて発注することも有効な対策です。例えば、雨が続く「梅雨」の時期や、台風が頻繁に上陸する「秋口」は、作業が中断しやすく、工期が読みづらくなります。また、積雪地帯においては、冬場は雪の影響で作業効率が著しく低下したり、作業自体が不可能になったりします。可能であれば、気候が安定している春(3月〜5月)や秋(10月〜11月)に着工できるよう計画するのが理想です。
施主様ご自身でできる、最も効果的かつ確実な工期短縮策です。建物内に家具、家電、布団、衣類などの「残置物」が大量に残っていると、業者はまずその分別・搬出作業から始めなければなりません。この作業だけで数日を要し、その分、建物本体の解体着工が遅れます。解体費用も余計にかかってしまいます。契約時までに建物の内部を空っぽにしておくことで、業者はスムーズに内装解体から着手でき、工期の大幅な短縮に繋がります。
工期延長の大きなリスクである「近隣クレームによる作業中断」は、事前の対策で防ぐことができます。業者が行う挨拶回りは当然ですが、可能であれば施主様も一緒に同行し、粗品(タオルや洗剤など)を持って「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」と一言添えてください。施主様が直接顔を見せて挨拶するだけで、近隣住民の方々の心証は全く異なります。良好な関係を築くことが、結果として工事をスムーズに進める保険となります。
業者との「意思疎通」も重要です。「いつまでに更地にしてほしい」という明確な希望日(例:家の売却日が決まっている、新築の着工日が決まっている等)がある場合は、必ず契約前に業者へ伝えてください。そのゴールに向けて、業者は最適なスケジュールを組んでくれます。また、工事が始まったら任せきりにせず、時々現場に顔を出したり、担当者に電話で進捗を確認したりすることで、業者の緊張感を保ち、作業の遅れを早期に把握することにも繋がります。
工期が長引く原因の「近隣クレーム」「アスベスト発見」「搬入経路の狭さ」は、プロの対応力が問われる部分です。私たちインシュアラは、1000件以上の実績で培った徹底した近隣配慮、有資格者によるアスベスト調査、小型重機を多数保有することで、あらゆる現場で遅延リスクを最小限に抑え、迅速な解体を実現します。
工期に関するトラブルの多くは、契約時の「確認不足」が原因です。「言った、言わない」の水掛け論を防ぐためにも、必ず「書面」で工期に関する取り決めを確認することが不可欠です。
契約前に、以下の点を確認しましょう。
見積書や契約書を受け取った際に、これらのポイントが明確になっているかをご自身の目でチェックしてください。
最も基本的な確認項目です。見積書や契約書に、工期に関する記載が一切ない業者は論外です。単に「工期:約〇日間」といった曖昧な記載だけでなく、可能であれば「着工予定日:〇年〇月〇日」「完工予定日:〇年〇月〇日」のように、具体的な日付が明記されているかを確認してください。これが、施主様と業者が共有する工事スケジュールの正式な約束事となります。
信頼できる業者は、契約後または契約前に、より詳細な「スケジュール表(工程表)」を提示してくれます。これには、「〇日〜〇日:養生足場設置」「〇日〜〇日:内装解体」「〇日〜〇日:躯体解体」といった、作業ごとの具体的な日程が記載されています。この工程表を事前に共有してもらうことで、施主様も今どの作業段階にあるのかを把握しやすくなり、業者の段取り力や計画性を見極める判断材料にもなります。
予定通りに工事が進まない場合に備え、「工期が延長する条件」を必ず書面(契約書)で取り決めておくことが重要です。例えば、「悪天候(台風、大雪など)により作業不能となった場合は、その日数を工期に順延する」「地中埋設物やアスベスト(レベル1,2)が発見された場合は、別途工期・費用を協議する」といった条項が契約書の約款に明記されているかを確認します。この取り決めがないと、遅延の責任の所在が曖昧になりトラブルの原因となります。
施主様が考える「工事完了」と、業者が考える「工事完了」にズレがないかを確認することも大切です。施主様は「建物が壊れた日」を完了日だと思いがちですが、解体工事はその後、基礎の撤去、整地、廃棄物の最終搬出までが作業範囲です。見積書の「完工日」が、これらすべての作業を終えて「きれいな更地で引き渡す日」を指しているのかを、契約前にしっかりと確認しておきましょう。
結局のところ、工期を適切に管理し、最短スケジュールで安全に工事を終えられるかどうかは、すべて「信頼できる業者」を選べるかにかかっています。
業者選びのチェックリストは以下の通りです。
価格の安さだけで判断せず、これらの基準を総合的に満たしているかを見極めてください。
これは法的な最低条件であり、信頼の土台です。解体工事を行うには、500万円以上の工事なら「建設業許可」、それ未満なら「解体工事業登録」が必須です。無許可業者は論外です。また、万が一の事故(隣家の破損など)に備え、「損害賠償責任保険」に加入しているかも必ず確認してください。これらの許可証や保険証券の提示を拒む業者は、絶対に選んではいけません。
業者の「実力」は、過去の実績に表れます。ホームページに、ご自身の物件と似たような木造解体の施工実績(写真付き)が豊富に掲載されているかを確認しましょう。また、Googleマップの口コミなどで、極端に悪い評価(特に近隣トラブルや追加請求に関するもの)が多くないかも参考になります。何より、見積もり依頼や質問への「対応スピード」は重要です。レスポンスが早い業者は、現場対応も迅速である可能性が高いです。
業者の「誠実さ」は、見積書と現地調査での対応に表れます。「工事一式」といった曖昧な見積もりではなく、各項目(養生費、本体解体費、廃棄物処分費など)の単価と数量が明記された「明朗会計」の見積書を提出してくれるかを見極めます。また、現地調査の際に、工期が延びるリスク(搬入経路が狭い等)や、近隣配慮の重要性をきちんと説明してくれる業者は信頼できます。
最も避けるべき業者です。契約書や工程表といった「書面」の取り交わしを軽視し、口約束ばかりで工事を進めようとする業者は非常に危険です。「とりあえず始めましょう」「何か出たらその時考えましょう」といった対応は、後で必ず「言った、言わない」のトラブルになります。また、「追加費用は一切かからない」と根拠なく断言する業者も、必要なアスベスト調査などを怠っている可能性があり、かえって危険です。
信頼できる業者の基準とは、突き詰めれば「誠実さ」と「実行力」です。私たちインシュアラは、建設業許可、各種保険加入はもちろん、自社施工・自社重機による「実行力」と、日本人スタッフによる「迅速で誠実な対応」をお約束します。見積もりは明朗会計を徹底し、工期についても明確にご提示します。安心してお任せください。
木造解体工事は、事前準備と業者選定で「早く・安全に・トラブルなく」終えられます。㈱インシュアラでは、1000件以上の実績と豊富な自社重機・人員を活かし、現地調査から近隣対応、行政申請までワンストップでサポートし、お客様のご事情に合わせた最短スケジュールで解体を完了させます。まずは無料相談であなたの建物に最適な工期を確認しましょう。