監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
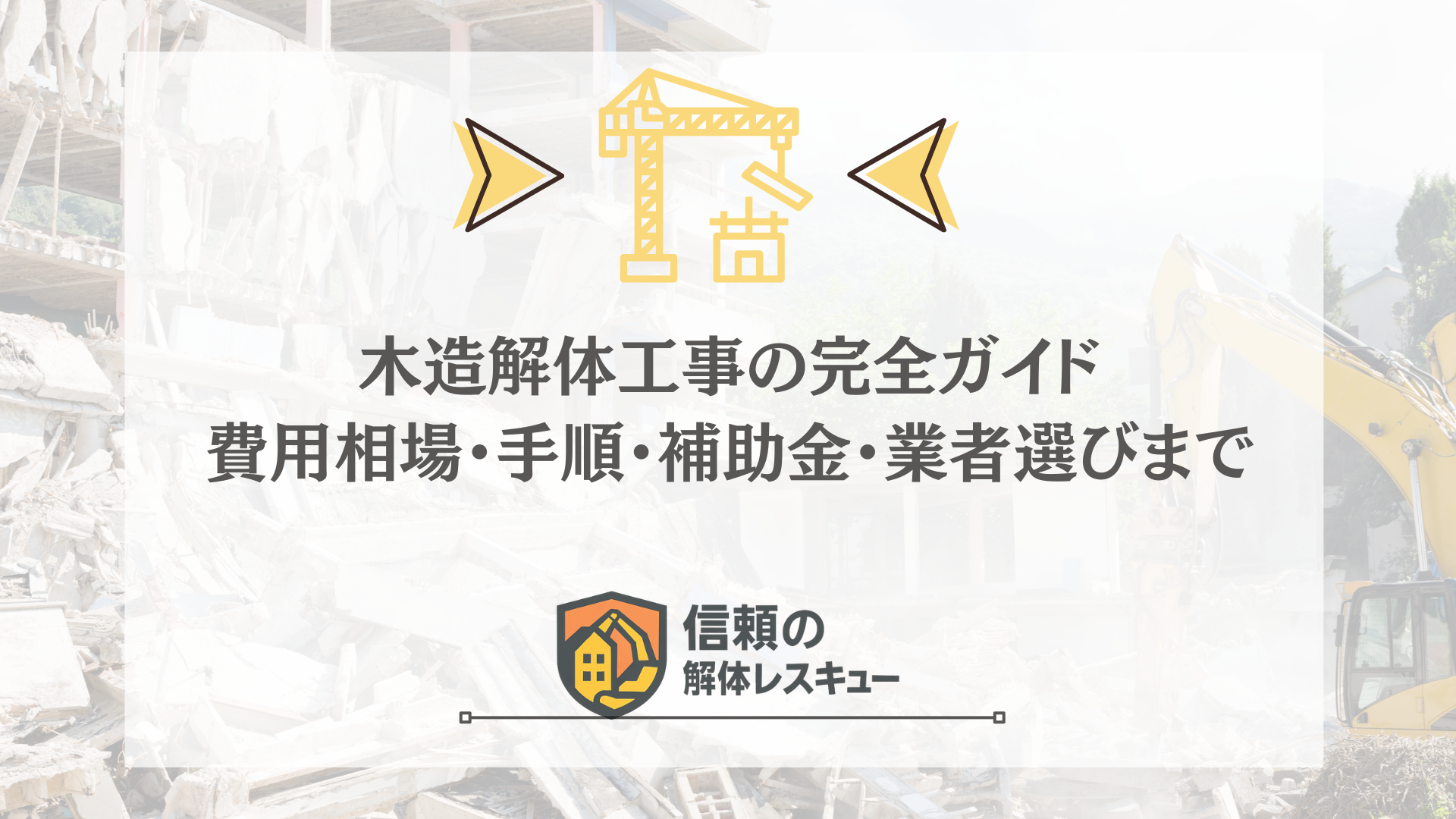
監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
ご所有の木造家屋やアパートの解体を検討される際、「費用はいくらかかるのか?」「何から手をつければ良いのか?」「近隣トラブルが心配だ」など、多くの不安があるかと存じます。木造解体は、単に建物を壊すだけでなく、法的な手続きや適切な廃棄物処理が求められる専門工事です。1000件以上の実績を持つ解体のプロとして、費用相場から内訳、コスト削減策、補助金、業者選びまで、後悔しないための全知識を徹底的に解説いたします。
木造解体工事は、建物を安全に取り壊し、法律に基づき廃棄物を適正に処理するまでの一連の作業を指します。RC造に比べ工期は短いものの、粉じんの飛散や騒音対策など、近隣環境への細やかな配慮が求められる工事です。まずは「何をどこまで行うのか」という工事の全体像を掴むことが重要です。
木造解体工事とは、建物本体(基礎含む)を取り壊し、更地にするまでを指すのが一般的です。しかし、契約内容は業者によって異なるため注意が必要です。例えば、本体の解体だけでなく、ブロック塀や物置、庭木といった「付帯物」の撤去も含むのかどうか。また、地中に埋まっている浄化槽や古い水道管の処理はどこまでか。工事範囲を明確に定義し、最終的にどのような状態で引き渡されるのか(例:整地レベル)を事前にすり合わせることが、トラブル回避の第一歩となります。
解体工法は主に3つあり、現場の状況で使い分けます。手壊しの割合が増えるほど、工期が延び、人件費がかさむため費用は高くなる傾向にあります。
| 工法 | 特徴 | 向いている現場(向き) | デメリット(不向き) |
| 手壊し | 人力で分別しながら解体 | 重機が入れない狭小地、隣家と密接 | 工期が長く、費用が最も高い |
|---|---|---|---|
| 重機解体 | 重機で一気に解体 | 敷地が広く、作業効率重視 | 騒音・振動大、狭小地は不可 |
| 併用工法 | 内装を手壊し、躯体を重機 | 現代のほとんどの現場 | (標準的な工法) |
工法の選定は、前面道路の幅や近隣環境に大きく左右されます。例えば、前面道路が4m未満で大型重機が進入できない場合、小型の重機を使用するか、最悪の場合は全て手壊しとなります。また、隣家との距離が1mもないような密集地では、安全確保と騒音・振動抑制のため、重機の使用を最小限にし、慎重な作業が求められます。このように、効率的な重機解体が可能かどうかが、工期と費用を決定づける重要な要因となるのです。
木造解体の坪単価相場は、1坪あたり4万円~6万円が目安です。ただしこれはあくまで建物本体の解体費用であり、総額は様々な条件で変動します。坪単価は、延床面積が広いほど割安に(坪単価が下がる)、狭いほど割高になる傾向があることも知っておく必要があります。
具体的な費用感を掴むために、面積別のシミュレーションをご覧ください。これはあくまで標準的な立地(重機進入可、付帯物標準)での概算です。正確な金額は必ず現地調査に基づいた見積もりを取得してください。
| 延床面積 | ① 本体解体費 (坪4.5万) | ② 付帯・諸費用 (概算) | 総額費用の目安 (①+②) |
| 20坪 | 約90万円 | 30万~50万円 | 120万~140万円 |
|---|---|---|---|
| 30坪 | 約135万円 | 30万~50万円 | 165万~185万円 |
| 40坪 | 約180万円 | 40万~60万円 | 220万~240万円 |
坪単価は一定ではありません。現場の「作業の手間」によって変動します。読者の皆様の物件がどちらに当てはまるか、自己診断の参考にしてください。
| 坪単価が下がる条件(安くなる) | 坪単価が上がる条件(高くなる) |
| 延床面積が広い(60坪以上など) | 延床面積が狭い(20坪以下など) |
|---|---|
| 敷地が広く、重機作業が容易 | 狭小地・密集地で手壊しが多い |
| 残置物や付帯物が少ない | ブロック塀、物置、庭石など付帯物が多い |
| 廃棄物処分場が近い | 処分場から遠い、搬出動線が悪い |
解体費用は、地域によっても差が出ます。物価や人件費が高い都市部は、地方に比べて高くなる傾向があります。また、廃棄物処分場までの距離もコストに影響します。処分場が遠ければ、トラックの運搬費がその分かかさむためです。弊社は「自社車両多数保有」により、この運搬コストを最適化しています。さらに、前面道路が狭く、大型ダンプが入れずに小型車で何度も往復(小運搬)が必要な場合も、運搬費が上昇する要因となります。
解体業者から提示された見積書は、総額だけでなく「内訳」を正しく読み解くことが重要です。何が含まれ、何が含まれていないのか。安く見えても、必要な項目が漏れていれば後から高額な追加費用が発生します。弊社の「明朗会計」は、内訳の透明性から始まります。
「本体解体費」または「木造解体工事費」という項目には、建物そのものを解体する作業の多くが含まれます。具体的には、工事着手前に設置する足場と養生シート(近隣への粉じん飛散防止)、重機や手作業による建物本体の取り壊し作業、そして解体で発生した木くずやガラをダンプトラックに積み込むまでの費用です。見積もりによっては、この「養生費」が諸経費として別計上されている場合もあります。
「付帯工事費」は、建物本体以外の撤去費用であり、見積もりから漏れやすい最たる項目です。現地調査の際に、これらを撤去するのか残すのかを業者と明確にすり合わせ、見積もりに反映してもらう必要があります。
【見積もり範囲の確認リスト】
本体工事費以外にかかる費用です。「処分費」は、解体で出た木くずやコンクリートガラなどを法律に基づき適正に処分場へ支払う費用です。「運搬費」は、その廃棄物を現場から処分場まで運ぶトラックの費用です。「諸経費」には、建設リサイクル法の届出代行、近隣挨拶、工事写真の作成といった事務手数料や現場管理費が含まれます。これらが「一式」ではなく、できるだけ具体的に記載されているかが重要です。
見積もり時に予測が難しく、後から追加費用として請求されやすい代表例です。契約前にこれらのリスクについて説明があるか、また、万が一発生した場合の取り決めが明確かを確認することが極めて重要です。
【要注意】追加費用が発生しやすいケース
「地中埋設物」は、解体工事で最もトラブルになりやすい項目です。弊社の「明朗会計」では、契約前に「もし古い基礎(地中障害)が出てきた場合、1㎥あたりいくら」という単価まで明確にお示しします。これにより、万が一の事態が発生しても、オーナー様が不当な高額請求に悩むことがないよう、リスクの透明化を徹底しています。
解体費用は高額ですが、オーナー様ご自身の「事前のひと手間」によって、余計なコストを大幅に削減することが可能です。見積もり依頼の前に、ぜひ実践していただきたい3つのポイントをご紹介します。
解体業者に室内の家具や家電、布団などの「残置物」の処分を依頼すると、「産業廃棄物」扱いとなり、非常に高額な処分費がかかります。しかし、オーナー様ご自身が事前に自治体のルールに従って「一般廃棄物」として処分すれば、その費用は数分の一で済みます。解体着工日までに、できる限り室内を空っぽにしておくこと。これが最も簡単で効果的なコスト削減策です。
「残置物」の処分は、オーナー様ご自身で対応いただくのが最もコストメリットが出ます。私どものような解体業者が代行すると、分別・搬出の人件費に加え、一般廃棄物の収集運搬許可を持つ業者への再委託費が上乗せされてしまいます。少しでも費用を抑えたい場合は、解体着工日までに「空っぽの状態」にしていただくことを強くお勧めします。
「この庭木は残したい」「このブロック塀は壊してほしい」といったご要望は、現地調査の際に必ず業者に明確に伝えてください。業者側も、どこまでが工事範囲かを正確に把握できるため、見積もりの精度が上がります。「壊すかどうか分からない」という曖昧な状態が、見積もりに不要なマージン(リスク費用)を上乗せさせる原因になります。解体範囲を明確化することが、見積もりのブレを防ぐコツです。
相見積もりは必須ですが、必ず「同条件」で比較してください。A社は「基礎撤去込み」、B社は「基礎撤去なし」では、総額が安くても比較になりません。「本体解体、基礎撤去、ブロック塀撤去、整地まで」といったように、全社に同じ条件を提示しましょう。また、必ず「現地立会い」のもとで見積もりを依頼してください。業者の人柄や、重機動線に関する具体的な提案力を比較できる絶好の機会となります。
木造解体工事は、契約から工事完了まで、多くのステップを踏む必要があります。全体の流れを把握しておくことで、オーナー様が「いつ・何をすべきか」が明確になり、安心して工事に臨むことができます。
解体工事において、予算と工期に最も大きな影響を与えるのが、アスベストや地中埋設物といった「見えないリスク」です。これらのリスクにどう備えるか、どのような契約を結ぶかが、解体工事の成否を分けると言っても過言ではありません。
2022年4月から、木造解体を含むすべての解体工事において、アスベスト(石綿)の事前調査が義務化されました。有資格者が図面と現地で調査し、その結果を都道府県に報告する必要があります。オーナー様もこの「調査報告書」の写しを業者から受け取り、内容を確認してください。「アスベスト含有の可能性のある建材あり」と記載されている場合は、次のステップに進むことになります。
アスベスト含有が疑われる場合のフローは以下の通りです。
地中埋設物(地中障害)は、実際に掘削してみないと分からない最大のリスクです。このリスクをヘッジするため、契約書には必ず「地中埋設物が発見された場合の取り扱い」についての条項を盛り込みます。例えば、「地中埋設物が発見された場合は、速やかに施主に報告し、その撤去費用は別途協議の上、合意した額を請求する」といった内容です。この条項が曖昧な業者は注意が必要です。
解体工事は高額ですが、自治体の補助金・助成金制度をうまく活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。これらの制度は、自治体の「空き家対策」の一環として設けられていることが多いです。
補助金は「申請の順番」が命です。必ず以下のステップを守ってください。
補助金申請は、「必ず契約前に申請する」というルールが鉄則です。先に契約してしまうと、ほぼ100%対象外となります。弊社はこれまでに多くの補助金活用案件を手掛けてまいりました。申請に必要な見積書の作成サポートも行っておりますので、「補助金を使いたい」と見積もり依頼時にぜひお声がけください。
補助金を申請する際、多くの場合、自治体に解体業者(1社または複数社)の見積書を提出する必要があります。この見積書が、補助金の対象となる工事(例:本体解体のみ)と、対象外の工事(例:残置物処分)が明確に分けて記載されていると、審査がスムーズに進みます。補助金の活用を検討している場合は、見積もりを依頼する業者にその旨を伝え、申請に対応した見積書を作成してもらうよう依頼しましょう。
解体工事の品質と安全性は、すべて「業者選び」にかかっています。価格の安さだけで選ぶと、不法投棄や近隣トラブルなど、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。1000件以上の実績を持つプロの目で、信頼できる優良業者を見極めるポイントをお伝えします。
【優良業者チェックリスト】
「少しでも費用を浮かせたい」と、ご自身で解体作業の一部を行おうと考える方もいらっしゃいますが、そこには大きなリスクが伴います。オーナー様ご自身で「できること」と、法令・安全上「絶対にやってはいけないこと」の線引きを解説します。
オーナー様ご自身で安全に作業できる範囲は、基本的に「残置物の処分」と「簡易な付帯物の撤去」までです。
【DIYで可能な範囲】
以下の作業は、法令違反や重大な事故に繋がるため、絶対にDIYで行わずプロに任せてください。
【プロに任せるべき作業(危険・違法)】
もし無許可で解体作業を行い、事故(隣家の破損など)を起こした場合、損害賠償責任はすべて作業を行ったオーナー様が負うことになります。保険も適用されません。また、解体で出た廃棄物を山林などに不法投棄した場合、その責任は業者だけでなく、排出事業者であるオーナー様にも及びます。プロに任せることは、これらの計り知れないリスクを回避するための最善の策なのです。
優良な業者を選んだ後も、契約内容の詰めと工事中の進捗管理が、トラブルを避けるためには重要です。「契約書にサインしたら、あとはお任せ」ではなく、オーナー様ご自身も要点を押さえておく必要があります。
契約書の中で最も重要な条項の一つが、「追加費用の取り決め」です。特に地中埋設物については、「地中障害が発見された場合は、速やかに施主に報告し、その処理方法と費用については別途協議の上、合意した額を請求する」といった内容が明記されているかを確認してください。「業者の判断で作業を進め、後から請求する」といった内容は危険です。必ず「事前報告・協議・合意」のステップが盛り込まれているかを確認しましょう。
解体工事は屋外作業のため、台風や大雪、長雨といった天候によって工期が遅延するリスクが常にあります。契約書には、「天災地変その他不可抗力により工事が遅延した場合、業者はその責を負わず、工期を延長できる」といった趣旨の条項(不可抗力免責)が一般的です。ただし、業者の段取り不足や人為的なミスによる遅延は、これに該当しません。遅延の理由が妥当であるかを判断するためにも、工程表は重要です。
工事が始まったら、現場の進捗を「可視化」してもらうことが重要です。優良な業者は、オーナー様が現場に足を運べなくても状況が分かるよう、自主的に「写真記録」を送ってくれます。例えば、「今日はここまで解体しました」「このように分別しています」といった写真付きの報告が定期的にあると安心です。弊社でも、お客様の不安を解消するため、日本人スタッフによるきめ細やかな進捗報告を徹底しています。
最後に、木造解体に関してオーナー様から特によく寄せられる質問をまとめました。1000件以上の実績を持つプロの視点から、皆様の疑問に明確にお答えします。
隣地との距離が1mを切るような現場でも、0.7m幅程度の超小型重機であれば進入できる場合があります。まずは現地調査で判断させてください。重機が入れない場合は手壊しとなり、工期と費用が増加します。騒音については、木造解体でも重機作業中は85dB(デシベル:救急車のサイレン程度)に達することがあります。弊社では防音シートで現場を囲い、作業時間を厳守することで、近隣への影響を最小限に抑えるよう努めています。
解体後の土地で新築を計画されている場合、解体業者と建築会社(ハウスメーカー)との連携が非常に重要です。例えば、次の新築工事で地盤改良(杭打ちなど)が決定している場合、解体業者は地中の古い杭を無理に引き抜かず、次の工事で干渉しない位置で切断(地切り)する方が、トータルコストが安くなる場合があります。弊社では、オーナー様、建築会社、弊社の三者で打ち合わせを行い、最適な整地レベルをご提案します。
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地の状況で課税されます。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で税金が安くなっていますが、解体して更地にすると、この特例が外れ、翌年から税額が上がります。もし年内に新築が完成しない場合、年を越して(例:1月2日以降に)解体する方が税制上有利な場合があります。また、解体完了後1ヶ月以内に「建物滅失登記」が義務付けられていますので、これは速やかに行ってください。
弊社、㈱インシュアラは、1000件を超える豊富な解体実績を誇る専門家集団です。木造解体において、他社にはない強みでお客様の不安を解消し、業界最安値水準と最高の安全をご提供します。
弊社は木造解体に特化したノウハウを蓄積しています。特に、廃棄物処分費を抑えるための「分別解体」を徹底しています。現場で木くず、プラスチック、石膏ボードなどを細かく分別し、再資源化率を高めることで、処分コストを最小限に抑えます。また、全スタッフが「近隣への配慮」を最優先事項として共有しており、ご挨拶から日々の清掃、迅速なクレーム対応まで、標準化された高いレベルでの現場運用をお約束します。
解体工事で最も不安な「追加費用」のリスクを最小限に抑えるため、弊社は事前診断に全力を注ぎます。図面と現地を目視するだけでなく、過去の同類事例から地中埋設物のリスクを予測します。その上で作成する見積書は、「一式」を極力排除した「明朗会計」がモッ”ト”ーです。アスベスト調査費用や、万が一地中障害物が出た場合の単価まで明記することで、お客様が納得の上でご契約いただける透明性を確保します。
弊社は、解体して終わり、ではありません。面倒な「補助金・助成金」の申請についても、自治体への提出書類(見積書など)の作成を全面的にサポートいたします。また、工事完了後に必須となる「建物滅失登記」についても、提携の土地家屋調査士のご紹介が可能です。調査から解体、そして完了後の手続きまで、ワンストップでお客様の負担を軽減できるのが弊社の強みです。
木造解体工事は、費用、安全、近隣配慮、法律手続きなど、考えるべきことが多いプロジェクトです。しかし、信頼できるパートナー(解体業者)を見つけることができれば、その不安の大部分は解消されます。まずは、ご自身の物件の適正価格を知ることから始めてみませんか。
弊社、㈱インシュアラでは、現地調査と見積もりを「完全無料」で承っております。1000件以上の実績を持つプロの目で、お客様の物件のリスクを診断し、最適な工法と適正な費用をご提案します。もちろん、相見積もりの1社としてご活用いただくだけでも大歓迎です。「同条件」で比較していただくため、弊社の見積もりはどこよりも詳細で明朗です。