監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
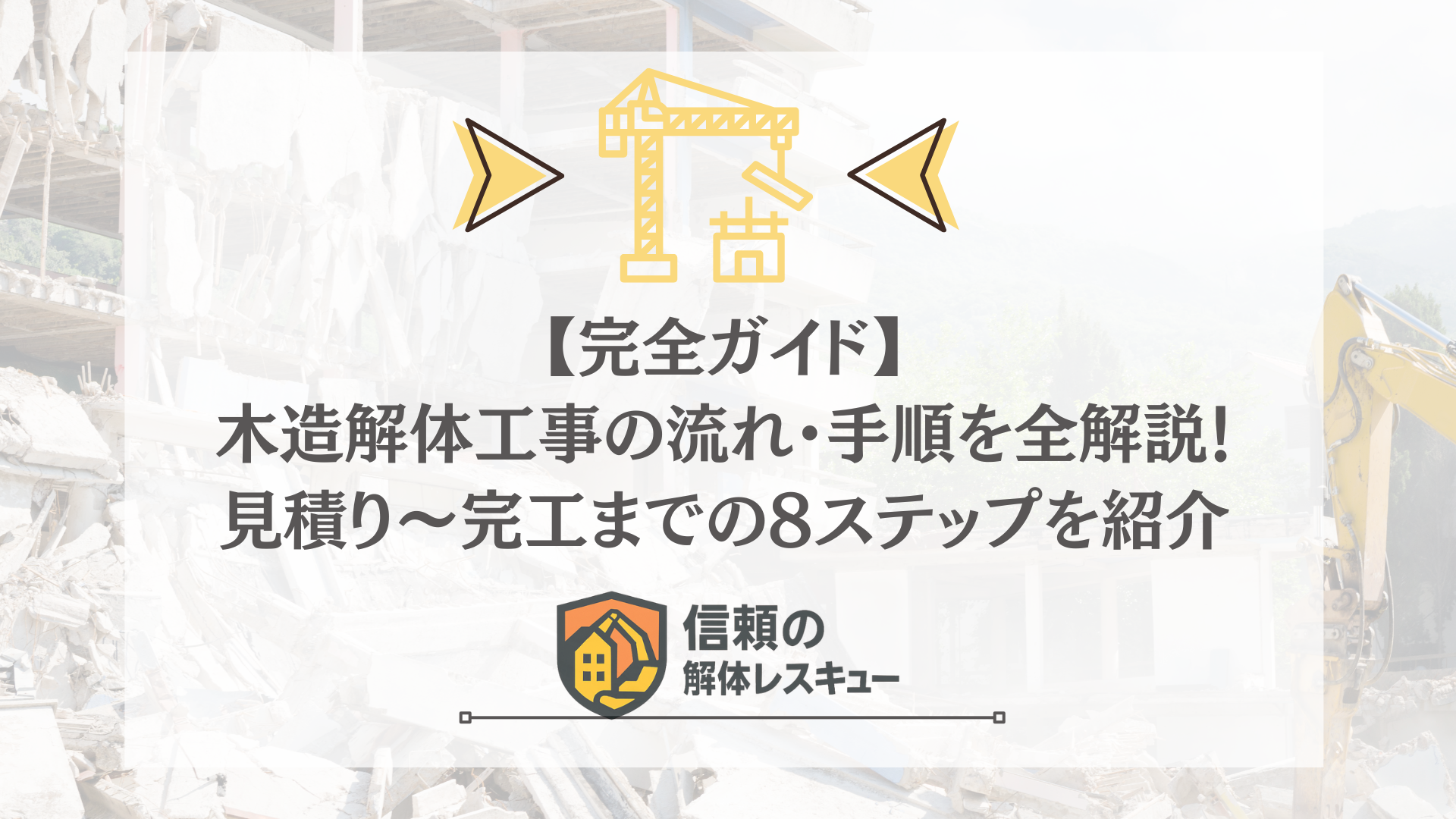
監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
「木造住宅の解体を考えているが、どの業者に頼めばいいか分からない」「見積もりを取ったが比較方法が不明だ」と悩んでいませんか。業者選びは解体工事の成否を分けます。本ガイドでは、1000件以上の実績から、失敗しない業者選びと見積もり比較の「核」となるポイントを徹底解説します。
木造解体には特有の注意点があります。まず「木造ならではの特徴」と「費用相場」を正しく知ることが、業者選びの第一歩です。構造が軽量な反面、分別作業が費用に直結します。基本を押さえなければ、適切な見積もり比較はできません。まずは適正価格の基準を知りましょう。
木造解体は、鉄骨造やRC造と異なり「分別作業」が命です。柱や梁の木材だけでなく、土壁、瓦、石膏ボードなど多様な素材が混在しているため、法律(建設リサイクル法)に基づき、これらを現場で手作業と重機を使い分け、細かく分別する必要があります。この分別の丁寧さが、最終的な廃棄物処分費、ひいては総額に直結します。また、軽量なため狭小地でも施工しやすい反面、隣家との距離が近い場合は、振動や騒音対策に高度な技術が求められるのが特徴です。
木造解体の費用相場は、坪単価で3万円~5万円が目安です。ただし、これはあくまで「建物本体」の解体費であり、総額ではありません。
【木造解体 費用相場(早見表)】
| 延べ床面積 | 費用相場(坪単価目安) | 総額目安(本体工事費) |
| 20坪 | 3万~5万円 | 60万~100万円 |
|---|---|---|
| 30坪 | 3万~5万円 | 90万~150万円 |
| 40坪 | 3万~5万円 | 120万~200万円 |
上記に加え「付帯物(ブロック塀や物置)の撤去費」「養生費」「廃棄物運搬処分費」が加算されます。都市部か地方か、重機が入れるかといった立地条件でも大きく変動するため、坪単価は参考程度に留め、必ず「総額」で見積もりを比較してください。
費用を賢く抑えるには、施主様ご自身の準備が鍵となります。業者の作業範囲を減らすことが、直接的なコストダウンに繋がります。
相見積もりは「総額」だけを比較しても意味がありません。最も重要なのは「なぜその金額なのか」という内訳を精査することです。最安値の見積書が、実際には最も高額になるケースは珍しくありません。これは、必要な項目(例:付帯物撤去費、廃棄物処分費、アスベスト調査費)が意図的に見積もりから抜かれており、契約後に追加請求されるためです。3社以上の見積もりを比較する際は、必ず「撤去範囲(塀・物置など)の条件が全社同じか」「『一式』表記で濁さず、品目別に単価が記載されているか」「追加費用が発生する条件は明記されているか」を確認してください。総額の安さではなく「見積もりの透明性」で業者を選ぶことが、最終的に費用を抑える最大のコツです。
 ㈱インシュアラ代表取締役社長 金松裕基
㈱インシュアラ代表取締役社長 金松裕基解体費用で不安なのは「見積もり後の追加請求」ですよね。弊社は「明朗会計」を徹底し、不要なマージンをカットした「業界最安値」に挑戦しています。自社施工だからこそできる透明な価格設定で、お客様の不安を解消します。まずはお見積もりをご比較ください。
解体工事は「準備」「施工」「事後処理」の3段階で進みます。全体の流れとスケジュール感を掴んでおくことは、業者の説明を理解し、計画通りに進めるために不可欠です。特に「解体前」の各種届出や手続きが重要であり、ここを怠ると工事が開始できません。全体の工程を把握しましょう。
工事着工前に、施主様が行うべき準備と業者が行う手続きがあります。
【施主様が行う準備】
【業者が行う手続き】
建設リサイクル法の届出
床面積80㎡以上の解体工事では、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。通常、業者が委任状をもらい代行します。
引用:国土交通省「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」
工事は、近隣配慮と法律遵守(分別)を徹底しながら、以下のステップで安全に進められます。
工事が完了したら、施主様は法的な手続きが必要です。
業者選びは解体工事の成否を9割決めます。価格の安さだけで選ぶのは最も危険です。「許可証」「保険」「契約書」など、会社の信頼性を測る重要項目が7つあります。これらを確認せず契約すると、不法投棄や高額な追加請求、近隣トラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
業者選びの7つのチェックリスト、特に「1. 許可証」「3. 保険」「5. マニフェスト」は、解体工事における「命綱」です。どれか一つでも欠けている業者に依頼すると、施主様ご自身が法的な責任や金銭的な賠償を負うリスクに直結します。私たちインシュアラは、これら全ての基準を高いレベルでクリアしていることをお約束します。
複数の見積もりを比較する際、単に総額だけを見てはいけません。「A社は安いがB社は高い」のには理由があります。「見積もりに含まれる項目」と「追加費用の条件」こそが重要です。特に一括見積サイト経由の業者は、手数料が上乗せされている可能性があり注意が必要です。
信頼できる見積書には、必ず以下の項目が内訳として明記されています。
「一式」表記が多い見積もりは避け、これらの内訳が明確な業者を選んでください。
契約後の追加費用は最大のトラブル源です。特に発生しやすいのは以下の3つのケースです。
優良業者は、契約前に「これらの事態が発生した場合、いくら追加費用がかかるか」を事前に明示してくれます。この「追加費用の取り決め」が曖昧な業者とは契約してはいけません。
一括見積サイトは便利ですが、その仕組みを理解する必要があります。サイト運営会社は、紹介した業者が成約すると、業者から「紹介手数料(中間マージン)」を受け取ります。そのコストが見積もりに上乗seされているため、割高になる傾向があります。
【依頼先による比較】
| 比較項目 | 直接依頼(インシュアラなど) | 一括見積サイト経由 |
| 費用 | 適正価格(中間マージンなし) | 割高(紹介手数料が上乗せ) |
|---|---|---|
| 業者の質 | 自分で直接見極め可能 | 不明(登録基準はサイト次第) |
| やり取り | 業者と直接(スムーズ) | サイト運営会社+複数業者(手間) |
適正価格を求めるなら、インシュアラのような自社施工業者への直接依頼が賢明です。
相見積もりは、価格交渉のためだけに行うのではありません。真の目的は「適正価格」と「業者の信頼性」を見極めることです。最低3社には依頼し、必ず「現地調査」に立ち会ってください。その際、撤去範囲(塀はどこまで、物置は含むか)など、全社に「同じ条件」を伝えます。出揃った見積もりを比較し、極端に安い(必要な項目が抜けている)業者や、高い(マージンが多い)業者を除外します。信頼できる1社を見つけるための作業です。



相見積もりは必ず取ってください。私たちインシュアラは、他社の見積もりと比較されることを大歓迎します。なぜなら、自社施工による「明朗会計」の見積もりに自信があるからです。追加費用が発生する条件もすべて事前に明示します。ぜひ、弊社の見積もりを「適正価格の基準」としてご活用ください。
契約後、業者に任せきりにするのは危険です。工事が適切に進んでいるか、施主様ご自身が「工事中」と「工事後」に確認すべき最低限のポイントがあります。これらを知っておくだけで、手抜き工事や近隣トラブルを未然に防ぎ、安心して工事を完了させることができます。
工事が始まったら、お時間がある時に以下の点をご確認ください。
気になる点があれば、すぐに現場監督に伝えてください。
工事が完了したら、必ず業者任せにせず「施主立会い」のもと最終確認を行います。
すべて確認し、納得した上で工事完了書にサインしてください。
トラブルの多くは「事前準備」と「契約時の取り決め」で防げます。
【よくあるトラブルと回避方法】
| よくあるトラブル | 回避方法 |
| 近隣クレーム(騒音・埃) | 丁寧な事前挨拶と、養生・散水を徹底する優良業者を選ぶ。 |
|---|---|
| 地中障害物による追加請求 | 契約前に「地中障害物発見時の追加費用」を書面で明確にする。 |
| 残置物による追加請求 | 工事開始前に、施主様ご自身で「残置物を完全撤去」しておく。 |
ここまでガイドを読んでいただいても、まだ細かな疑問が残るかもしれません。施主様から特によく寄せられる質問をFAQ形式でまとめました。
必須なのは「現地調査」です。可能であれば「建物の図面(配置図・平面図)」や「登記簿謄本(面積や構造がわかるもの)」をご用意いただくと、より正確な見積もりが迅速に作成できます。最も重要なのは、現地調査の際に「どこまで解体・撤去したいか(塀、物置、庭木など)」をご自身の言葉で明確に伝えることです。
標準的な30坪程度の木造住宅で、準備(足場・養生)から解体・整地、後片付けまで含めて、実働で「約10日〜2週間」が目安です。ただし、これは天候に恵まれた場合の最短スケジュールです。雨天や強風の日は安全のため作業を中断するため、工期は延びる可能性があります。また、狭小地で手壊し作業が多い場合や、アスベスト除去が必要な場合は、さらに日数がかかります。
自治体によって利用できる場合があります。代表的なものは「老朽危険家屋解体撤去補助金」や「空き家対策補助金」です。自治体ごとに名称や条件(耐震基準、築年数など)、補助金額(上限50万~100万円など)が異なります。注意点は「必ず契約前に申請が必要」であることです。「〇〇市 解体 補助金」などで自治体のホームページを確認するか、窓口に直接相談してください。
補助金の申請は、施主様ご自身で行うには手続きが煩雑な場合が多いです。私たちインシュアラは、解体工事だけでなく、こうした行政手続きに関するご相談も承っています。「自分の家が対象になるか分からない」といった初期段階のご相談からサポート可能ですので、お気軽にお声がけください。
木造解体工事の成功は、9割が「業者選び」にかかっています。本ガイドで解説したポイントを実践し、信頼できるパートナーを見つけることが、適正価格で、安全かつ近隣に配慮した解体を実現する唯一の方法です。価格だけでなく、透明性、技術力、対応力を総合的に判断してください。
1000件以上の解体工事を手がけてきた経験から断言できるのは、「施主様の不安に寄り添えない業者は、良い工事もできない」ということです。私たちは、自社施工による中間マージンを排除した「適正価格」と「明朗会計」はもちろん、日本人スタッフによる「迅速な対応」と「徹底した近隣配慮」を何よりも大切にしています。お見積もりは無料です。他社の見積もりと比較するためでも構いません。ぜひ一度、私たちにご相談ください。