監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
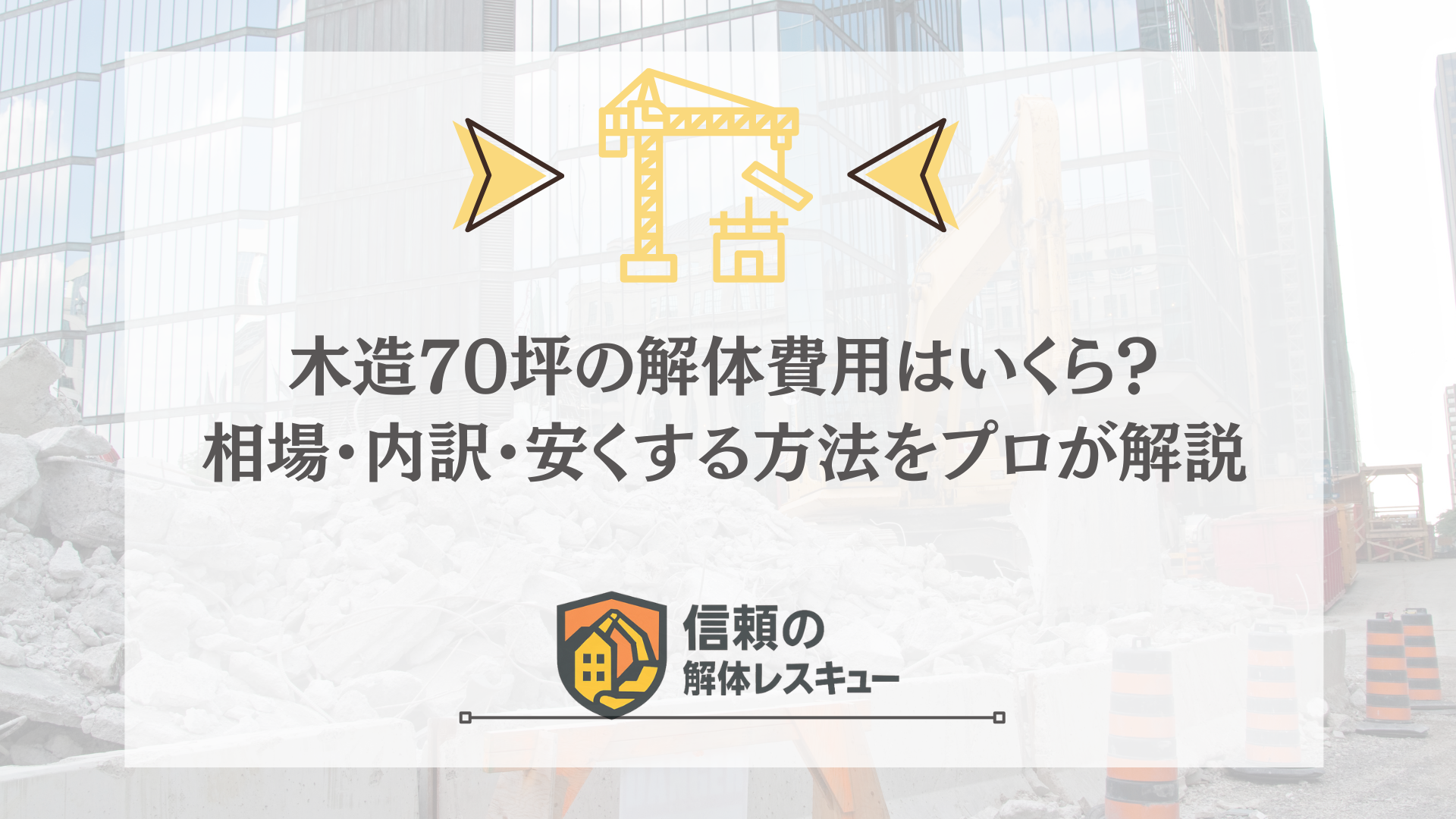
監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。
木造70坪という広い家の解体を前に、まず「費用がいくらかかるのか」が最大の関心事ではないでしょうか。解体費用は、坪単価だけで決まるほど単純ではありません。この記事では、1000件以上の解体実績を持つ㈱インシュアラが、70坪の木造解体費用のリアルな相場、費用の内訳、そして合法的に費用を抑える具体的な方法まで、プロの視点で徹底的に解説します。
木造70坪の解体費用は、あくまで目安ですが180万~400万円前後(坪単価2.5万~6万円)が相場です。ただし、これは建物本体の解体費です。立地や付帯工事の有無で総額は大きく変動するため、なぜ費用差が出るのかを知ることが重要です。
70坪の木造住宅解体費用は、一般的に180万円から400万円程度を見込む必要があります。坪単価で言えば、約2.5万円から6万円が相場です。なぜこれほど幅があるかというと、都市部か地方か、重機が入りやすいか、廃材の処理費用がいくらか、といった諸条件が業者ごとに異なるためです。例えば、都心部で道が狭ければ人件費や運搬費が嵩みます。この相場はあくまで概算であり、実際の金額は見積もりを取るまで確定しないことを理解しましょう。
解体費用は「坪単価 × 延床面積(坪数)」で大まかな目安を計算できます。例えば、坪単価3万円の業者が70坪の木造住宅を解体する場合、3万円×70坪=210万円が一つの目安です。しかし、この計算には注意が必要です。この「坪単価」にどこまでの作業(例:足場代、廃材処理費、整地費)が含まれているかが、業者によってバラバラだからです。坪単価が安く見えても、後から多くの追加費用が発生するケースもあります。坪単価はあくまで入り口の目安として捉え、総額で見積もりを比較することが肝心です。
同じ70坪でも、A邸が250万円、B邸が380万円になるケースは珍しくありません。この費用差は「付帯工事」と「立地」が主な原因です。B邸には重厚なブロック塀、大きな庭石、カーポートがあり、これらが追加費用となります。さらに道が狭く重機が入れなければ、手作業が増え人件費が嵩みます。建物の状況一つひとつが費用に直結します。
【70坪 解体費用比較事例】
| A邸(安い例) | B邸(高い例) | |
| 総額 | 250万円 | 380万円 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 約3.5万円 | 約5.4万円 |
| 建物 | 木造70坪 | 木造70坪 |
| 追加要因 | ・特になし ・前面道路 6m | ・重厚なブロック塀の撤去 ・大きな庭石、庭木の撤去 ・カーポート撤去 ・前面道路 2m(重機搬入不可) |
坪単価はあくまで目安です。特に70坪規模では、塀や庭の状態、道路の幅で100万円単位の差が出ます。見積もりを取る際は「総額」と「追加費用の可能性」を必ず確認してください。
解体費用は「総額いくら」ではなく、その「内訳」を理解することが非常に重要です。見積書が読めれば、不当に高い費用や、必要な作業が含まれているかを判断できます。解体工事は主に「仮設」「本体工事」「廃材処理」「整地」で構成されています。
【解体費用の主な内訳】
仮設工事とは、解体作業を安全に行うための準備作業です。具体的には、作業員の足場や、粉塵・騒音を防ぐための養生シート(防音シート)の設置が含まれます。70坪規模の住宅となれば、建物の周囲を広範囲に覆う必要があるため、足場・養生費用も高額になる傾向があります。この仮設工事は、解体作業の品質と近隣住民への配慮に直結する重要な項目です。見積書でこの項目が極端に安い場合は、安全対策が不十分でないか確認が必要です。
解体作業本体の費用とは、文字通り建物を重機や手作業で壊していく作業費、つまり「人件費」と「重機代」です。木造70坪となると、建物の規模が大きいため、相応の作業日数と人員が必要になります。また、重機がスムーズに入れる立地であれば効率的に作業が進みコストは抑えられますが、狭い場所では小型重機を使ったり、手壊しの割合が増えたりするため、人件費が上昇します。この項目が、総費用のうち大きな割合を占めることになります。
解体工事で最も費用に影響するのが、廃材の搬出・処理費用です。木造住宅からは、木くず、コンクリートガラ(基礎)、石膏ボード、ガラス、金属くずなど、多種多様な廃材が発生します。70坪の家ともなれば、その廃材量は膨大です。法律(建設リサイクル法)に基づき、これらを分別し、適切に中間処理施設へ運搬・処分する必要があります。処分費用は廃材の種類や重さ、地域の処理場の価格によって変動します。不法投棄を防ぐためにも、この費用が適正に計上されているか確認が不可欠です。
解体作業が完了した後、土地を平らにならす作業を「整地」と呼びます。解体後の土地をどのように利用するか(新築、売却、駐車場など)によって、整地の仕上げレベルが変わります。単にコンクリートガラなどを取り除き、重機で踏み固める「粗仕上げ(粗整地)」が一般的ですが、売却や新築を見据えて砂利を敷いたり、コンクリートで舗装したりする場合は別途費用が発生します。どこまでの仕上げを希望するかを、事前に業者と明確にすり合わせておくことが重要です。
見積書には「諸経費」や「現場管理費」といった項目も記載されます。これには、現場監督の人件費、工事車両のガソリン代、近隣への挨拶回りの費用、役所への申請書類作成(建設リサイクル法の届出など)の代行手数料などが含まれます。一般的には総工費の5〜10%程度が目安です。ただし、この項目が「一式」とだけ書かれていて内訳が不明瞭な場合は、具体的に何が含まれているのかを業者に確認すべきです。明朗会計な業者は、この諸経費の内訳も説明してくれます。
見積書で最も重要なのが「廃材処理費」と「諸経費」です。特に「諸経費 一式」としか書かれていない場合は要注意。㈱インシュアラは明朗会計を徹底し、何にいくらかかるかを丁寧にご説明します。
70坪クラスの木造住宅は、一般的な30〜40坪の住宅と比較し、単なる面積比以上に費用が高額化しやすい要因を抱えています。廃材の量、立地条件、そして付帯物の多さが、坪単価を押し上げる主な理由です。
【70坪の解体が高額になる5つの理由】
解体費用は、突き詰めれば「廃材の量」と「人件費(作業日数)」で決まります。70坪の住宅は、単純に35坪の住宅の2倍の廃材が出るわけではありません。柱や梁が太く、基礎も頑丈に作られているケースが多く、廃材の「体積」と「重量」が想定以上に増加します。廃材が多ければ、処分費と運搬回数が増加します。同様に、建物を壊す作業日数と、分別にかかる人件費も増大するため、総額が高額になりやすいのです。
70坪の立派な家が建っていても、そこに至る道が狭い(狭小道路)ケースは少なくありません。特に、4トントラックや大型重機が現場の目の前まで入れない場合、コストは跳ね上がります。重機が入れなければ、解体作業の多くを「手壊し」に頼るしかなく、人件費が激増します。また、廃材をトラックまで手作業や小型運搬車で何度も往復して運び出す(小運搬)必要も生じます。この「小運搬費」や「手壊し費用」が、見積書に上乗せされることになるのです。
古い70坪の家屋の場合、現在の建築基準では想定されない物が地中から見つかるリスクが高まります。昔の井戸、浄化槽、または以前の建物の基礎(地中梁)などが「地中埋設物」として発見されると、これは見積もり外の「追加費用」となります。また、70坪の大きな建物を支えていた「基礎」も、当然ながら大規模で頑丈です。この基礎コンクリートを破砕し、搬出する作業は、解体工事の中でも特にコストがかかる部分であり、費用を押し上げる要因となります。
70坪クラスの住宅が建てられた年代(特に2006年以前)によっては、アスベスト(石綿)が使用されている可能性があります。アスベストは健康被害を引き起こすため、解体時には飛散防止のための厳重な除去作業が法律で義務付けられています。
【アスベストのレベルと危険度・費用目安】
| レベル | 危険度 | 主な使用箇所 | 費用目安(例) |
| レベル1 | 非常に高い | 吹き付け材(耐火被覆など) | 100万円~ |
|---|---|---|---|
| レベル2 | 高い | 保温材(配管など) | 20万円~ |
| レベル3 | 比較的低い | 屋根材(スレート)、外壁材 | 5万円~ |
70坪の家は、敷地自体も広いことが一般的です。そのため、建物本体以外に解体・撤去すべき「付帯物」が多い傾向にあります。これらはすべて、建物本体の解体費用とは「別料金」として加算されます。
【主な付帯工事(追加費用)の例】
特に樹木の伐採・伐根や、重機が必要な庭石の撤去は高額になりがちです。見積もり時には、どこまでを解体範囲に含めるかを明確に指示することが重要です。
70坪規模で最も怖いのが「地中埋設物」と「アスベスト」です。これらは見積もり段階では見えないため、優良業者は必ず「もし発見された場合の追加費用」についても事前に説明します。見積もりにこの説明がない業者は注意が必要です。
解体業者の当初の見積もりは、あくまで「建物本体」と「目視できる付帯物」に対するものが基本です。工事が始まってから発覚する unforeseen(予期せぬ)事態により、追加費用が発生する可能性があります。これらを事前に把握しておくことが重要です。
これらは「付帯工事」と呼ばれ、建物本体の見積もりとは別に計上されるのが一般的です。特に70坪の家では、敷地を囲う塀やブロックの長さも相当なものになります。コンクリートブロック塀の撤去は、重機作業や運搬費がかかるため、1メートルあたり数千円〜1万円程度の費用が追加されます。古い物置やカーポートも同様です。見積もり時に「建物以外で撤去してほしいもの」を全て業者に伝え、それらが費用に含まれているかを必ず確認してください。
庭の大きな樹木(伐採・伐根)や、重さのある庭石の撤去は、専門の重機や技術が必要となり、高額な追加費用となる代表例です。また、家の中に残された家具、家電、布団などの「残置物」の処分を解体業者に依頼すると、産業廃棄物ではなく「一般廃棄物」としての処理費用がかかり、非常に割高になります。解体業者によっては残置物の処分自体を請け負わない場合もあります。これらは可能な限り、解体工事が始まる前にご自身で処分(整理)しておくべきです。
解体工事で最もトラブルになりやすいのが、この「地中埋設物」です。建物の基礎を撤去した後の地中から、以前の建物の基礎、古い浄化槽、井戸、コンクリートガラ、時には大量のゴミが発見されることがあります。これらは見積もり時の現地調査では予測不可能であり、撤去・処分費用は原則として「追加請求」となります。70坪の広い敷地の場合、このリスクは常にあると認識し、予期せぬ出費として予算を確保しておくことが賢明です。
アスベスト(石綿)が使用されていた場合、その除去費用は法律で定められた厳格な作業(隔離、湿潤化、専門作業員による除去)が必要となるため、高額になります。費用の目安は、アスベストのレベル(発じん性)や使用箇所、面積によって大きく変動します。例えば、発じん性が比較的低いとされる屋根材(スレート)の除去でも数十万円、内装の吹き付けアスベスト(レベル1)などが見つかると、数百万円規模の費用になることもあります。これらは専門的な調査が必要であり、見積もりとは別枠で請求されます。
追加費用で最も多いのが「残置物」です。㈱インシュアラでは、残置物の処分もまとめてお引き受け可能ですが、費用を抑えるならご自身での処分が一番です。どこまでをご自身でやり、どこからを業者に任せるか、見積もり時にご相談ください。
70坪の解体費用は高額になりがちですが、無駄なコストを削減し、賢く費用を抑える方法は確実に存在します。重要なのは「比較」と「事前準備」、そして「業者の選び方」です。専門業者(㈱インシュアラ)の視点から5つの秘訣をお伝えします。
【解体費用を抑える5つのポイント】
解体費用を抑えるための第一歩であり、最も重要なポイントです。必ず3社程度の解体業者から「相見積もり」を取りましょう。70坪規模の解体では、業者によって得意・不得意や重機の保有状況が異なり、見積もり額に数十万円、時には100万円以上の差が出ることも珍しくありません。ただし、単に総額が安い業者を選ぶのは危険です。見積書の「内訳」を比較し、必要な作業(例:整地、廃材処理)が全て含まれているか、不自然に安い項目はないかを確認することが重要です。
家の中の家具、家電、衣類、布団などの「残置物」は、可能な限りご自身で処分してください。解体業者がこれらを処分する場合、専門の許可(一般廃棄物収集運搬業)が必要となり、自治体の処分費用よりもはるかに高額な「産業廃棄物」扱いの料金(または高額な手数料)を請求されることになります。70坪の家ともなれば残置物の量も膨大です。解体工事の契約前に、リサイクル業者に売却したり、自治体の粗大ごみ収集を利用したりして、家の中を空っぽの状態にしておくことが、数十万円単位の節約に直結します。
解体業界にも「繁忙期」と「閑散期(オフシーズン)」があります。一般的に、年度末(1〜3月)や公共工事が増える時期は繁忙期となり、業者のスケジュールが埋まり、見積もり額も強気になる傾向があります。逆に、梅雨時期(6月)や真夏(8月)などは、天候の影響で作業がしにくいため、比較的スケジュールに余裕が出やすい時期です。工事の時期を急がないのであれば、あえてこうしたオフシーズンに工事を依頼することで、価格交渉がしやすくなる可能性があります。
お住まいの自治体によっては、解体工事(特に老朽化した空き家)に対して補助金・助成金制度を設けている場合があります。70坪の家が「特定空き家」に指定されている場合や、自治体の定める耐震基準を満たしていない古い建物の場合、解体費用の一部(例:費用の1/5、上限50万円など)が助成される可能性があります。これらの補助金は、必ず「解体工事の契約前」に申請する必要があります。まずは「(自治体名) 解体 補助金」で検索し、制度の有無を確認してみましょう。
解体業者には、工事を下請けに丸投げする「元請け(ブローカー)」と、自社で重機と職人を抱えて直接工事を行う「自社施工(専門業者)」がいます。元請け業者に依頼すると、当然ながら中間マージン(紹介料)が発生するため、その分費用が高くなります。㈱インシュアラのような自社施工業者は、この中間マージンが不要なため、適正価格で高品質な工事を提供できます。業者のウェブサイトで重機やスタッフの紹介があるか、許可証(建設業許可)を持っているかを確認し、直接施工する業者を選ぶことが重要です。
費用を抑える最大の秘訣は「自社施工」の業者を選ぶことです。㈱インシュアラは、自社重機・自社スタッフで対応するため、中間マージンが一切発生しません。これが「業界最安値」を提示できる理由です。相見積もりの際は、ぜひ当社の「明朗会計」見積もりと比べてみてください。
70坪の家であっても、一定の条件(主に老朽化や空き家であること)を満たせば、自治体の補助金・助成金制度を利用できる可能性があります。解体費用は高額なため、活用できる制度は漏れなくチェックし、賢くコストを抑えるべきです。
多くの自治体が「空き家対策特別措置法」に基づき、「老朽家屋除却補助金」や「空き家解体助成金」といった名称で制度を設けています。これは、倒壊の危険性がある、または景観や衛生環境を著しく損ねていると判断された「特定空き家」や「管理不全空き家」の解体を促進するための制度です。70坪の家であっても、これらの条件に合致すれば対象となる可能性があります。補助額は自治体により様々ですが、解体費用の20%〜50%(上限額30万〜100万円程度)が一般的です。
引用:例:東京都足立区「老朽家屋の解体費用助成」
補助金を利用する場合、流れを把握することが重要です。
【補助金申請の基本ステップ】
【主な必要書類(例)】
これらは一例です。自治体ごとに必要書類は異なりますので、必ず事前に確認してください。
補助金活用で最も注意すべきは「フライング」です。自治体からの「交付決定通知」を受け取る前に、解体業者と「工事請負契約」を締結してしまうと、その時点で補助金の対象外となってしまいます。また、申請には期限(例:予算がなくなり次第終了)があるため、解体を決めたらすぐに自治体の建築指導課や空き家対策担当窓口に相談することが重要です。税金(固定資産税)を滞納している場合も対象外となることが多いため、事前に確認が必要です。
補助金の申請は、書類が非常に煩雑です。自治体によっては、見積書だけでなく「なぜ解体が必要か」の理由書を求められることも。㈱インシュアラは、こうした補助金申請に必要な書類(見積書、図面など)の作成サポートも迅速に対応します。
70坪の解体工事は、規模が大きいため工期も長く、近隣への影響も大きくなります。トラブルなくスムーズに工事を終えるためには、依頼前の準備と工事全体の流れを正確に把握しておくことが不可欠です。
まずは、解体業者に現地調査を依頼します。70坪の場合、建物本体だけでなく、外構や道路状況をプロの目で見てもらうことが重要です。その後のステップは以下の通りです。
【契約までの流れ】
契約時には、工事の範囲、工期、支払い条件、追加費用発生時のルールを書面で明確にしておくことがトラブル防止の鍵です。
70坪規模の解体では、騒音、振動、粉塵(ほこり)の発生は避けられません。工事開始前に、業者が近隣住民の方々へ挨拶回りを行い、工事概要や工期、緊急連絡先を説明することが必須です。優良な業者は、この近隣対応を非常に丁寧に行います。また、作業中は足場と養生シートで現場を囲い、粉塵の飛散防止のために散水を徹底するなど、安全管理と環境配慮が求められます。㈱インシュアラでは、この近隣配慮と安全管理を最重要視し、クレームゼロの現場運営を心がけています。
工事が完了すると、業者が廃材を全て撤去し、土地を平らに整地して引き渡しとなります。しかし、施主様(お客様)がやるべき重要な手続きが残っています。それは「建物滅失登記」です。建物がなくなったことを法務局に届け出る義務があり、解体後1ヶ月以内に申請が必要です。これを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。また、建物がなくなると土地の固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、翌年からの税金が上がる可能性についても理解しておく必要があります。
70坪の解体は近隣への影響が大きいため、業者の「近隣対応」の質が非常に重要です。㈱インシュアラでは、工事前の挨拶はもちろん、工事中も日本人スタッフが丁寧に対応し、万が一のクレームにも迅速に対応します。
70坪クラスの大規模な解体を任せる業者は、安さだけで選んではいけません。不法投棄や近隣トラブル、高額な追加請求といったリスクを避けるため、「信頼できる専門業者」を見極める目が必要です。
【優良な解体業者のチェックリスト】
まず最低条件として、業者が「建設業許可(解体工事業)」または「解体工事業登録」を持っているかを確認します。これがない業者は違法です。次に、廃材を適正に処理したことを証明する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行に対応しているかを確認しましょう。マニフェストは、不法投棄を防ぎ、施主様(お客様)が最終的な処理責任を問われないために非常に重要です。70坪の膨大な廃材を適正に処理するコンプライアンス意識があるかを見極める必須のチェックポイントです。
前述の通り、業者には「自社施工」と「下請け丸投げ(元請け)」がいます。70坪の解体費用は高額なため、中間マージン(紹介料)の有無は、総額に数十万円単位で影響します。ウェブサイトで「重機保有」「有資格者の在籍」「日本人スタッフ対応」などを明記しているか確認しましょう。㈱インシュアラのように、自社で重機と専門の職人を抱えている業者は、コストを抑えられるだけでなく、現場の安全管理や技術力、緊急時の対応(迅速対応)においても、丸投げの業者とは比較にならない安心感があります。
解体工事は「壊して終わり」ではありません。解体後の土地活用(新築、売却、駐車場経営など)を見据えている場合、その後の手続き(例:建物滅失登記、整地の仕上げ方)についても相談できる業者が理想です。70坪という価値ある資産だからこそ、解体後の整地をどのように仕上げるか(粗仕上げか、砂利敷きか)は重要です。解体実績が豊富な業者は、滅失登記の代行(提携司法書士の紹介)や、次のステップに進みやすい整地方法の提案など、解体後も見据えたトータルサポートが可能です。
業者選びは「許可証の有無」と「自社施工」が二大ポイントです。㈱インシュアラは、もちろん建設業許可を保有し、100%自社施工です。当社の1000件以上の実績と、有資格者である日本人スタッフが、お客様の70坪の大切な資産の解体を安全・適正価格で実行します。
木造70坪の解体費用は高額ですが、その内訳や高額になる理由を理解すれば、適正価格が見えてきます。「坪単価」だけにとらわれず、「相見積もり」で複数の業者を比較し、自治体の「補助金」も活用する。そして何より、中間マージンのない「自社施工」の専門業者を選ぶこと。これらが、70坪の解体工事を賢く、安く、安全に進めるための最大の秘訣です。